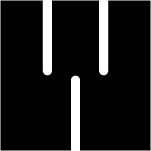日本での危機対応の要諦はトップ会見にある
日本での企業で不祥事が発生した際にマネジメントが取るべき対応の要点は、他国と変わるところはない。
- 被害の最小化または損害の賠償を行う計画を進めつつ
- 発生原因の究明を行い
- 原因に基づいて責任を明確にして処分を決め
- 実効性のある再発防止策を策定し
- これらの手順、経緯を早期に公表すること
これらの対応は、東京証券取引所を運営する日本取引所グループが、不祥事が起きた場合に企業がとるべき対応のプリンシプルとして定めている。(https://www.jpx.co.jp/english/news/3030/20180330.html : “Publication of Principles for Preventing Corporate Scandals”)
企業が、危機対応で企業のレピュテーションを下げてしまうのは、被害者に誠意に欠ける対応をした場合、自社の責任を認めなかったり、謝罪が不十分であった場合、経緯や原因究明の説明があいまいであったり、修正が多かったり、調査に時間がかかったりした場合である。
日本での危機対応で、海外諸国での危機対応と顕著に異なる点を一つ挙げるとすれば、不祥事の原因が社員にあった場合の企業トップに対しての責任の考え方であろう。日本では、企業不祥事にはトップが記者会見を開いて事件の説明を謝罪を行う。その際にたとえトップが直接事件にかかわっていなくても、トップの責任を追及する場合がある。その取り方として「辞任」の意思について会見で質問する、というより、「辞任」を迫る場面がある。
メディアがトップの責任を追求するのは、組織の長としてトップが「組織を適切に運営する能力に欠けているのではないか」、「従業員が不正を行った原因の背景には、従業員に不正を起こさせない仕組み作りができていなかったのではないか」「不正の原因は、企業風土に基づいているのではないか」という疑念を持った場合である。この疑念の根底には、「権力をもった者は、引き際を潔くすべきだ」という日本的な考え方もある。ある謝罪会見では「再発防止をしっかり講じることが自分の責任」として、職務の遂行を主張したトップに対して、記者が同じような不祥事を起こした他の企業のトップが辞任したことを引き合いに出して「潔くない」と辞任を迫った。早々にトップが「引責辞任表明」をしたため、メディアの責任追及の圧力が弱まり、その後は、事実関係のみを伝えるニュートラルな報道になった場合もある。
記者会見は、事件についての警察の捜査や裁判所の判断が終わっていない時点で開催することが多いため、トップが早々と自分の責任を表明することは多くのリスクがある。企業トップは、様々なステークホルダーを勘案して、事態の早期収拾、事業及びレピュテーションへの影響の最小化、事業継続という責任を果たすために、自らの進退や処分を決めるという難しい決断をしなければならない。
従って、日本では、どの時点で、トップによる記者会見を行うか、何について責任を認め、誰に謝り、誰がどのように責任とることを表明するか・・という点が、危機対応のコミュニケーションの成否を決める大きなポイントとなる。